稟議書での追加の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

稟議書での追加の書き方の用途
稟議書とは、一般企業等での部下から上司への伺いのことを一般的に指していうものです。民間企業ではなく役所等の場合は、起案書あるいは起案とも言い換えたりします。この文書を持って、必要な上司への説明及び了解を押印してもらうことで了解を得る行為となります。追加の書き方としては、通常いったんこの稟議書が却下あるいは止められた場合に必要な書類を付け加えることで、処理を可能にするためのもの等が該当します。
稟議書での追加の書き出し・結びの言葉
書き出しとしては、どこまで書類が回ったのかにもよりますが、すでに最終決裁者まで決裁がなされている場合と、途中で止まっている場合とで書き方が多少異なります。すでに最終決裁者まで書類に押印されている場合には、別の稟議書を用意して補足する方法が一般的にとられますし、必要書類を追加で補足説明として添付する場合には、先の決裁を受けてと言う書き出しで始まるものとなります。
稟議書での追加の書き方の例文・文例01
稟議書ですから、社内規定等により数年間は保存しなければならないものです。すなわち、雛形や例文等としてすでにあるものを参考にして作成も可能であり、従前通りで問題がないこともあることから、年度や数字などを修正したものをもって、上司に伺いとして使用することが一般的となります。なお、金額等の重要な訂正の場合には、修正の稟議書を改めて挙げる場合もあるため注意しなければいけません。
稟議書での追加の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
追加で稟議書を挙げる場合ができる場合と総出ない場合とがあることです。すなわち、軽微な内容の修正ではあるけれども、修正が必要な場合には、追加資料として添付することもあります。ただし、金額等の訂正のように重要な場合には、稟議書そのものをやり直すかあるいは稟議書を改めて修正して再度上司に見せなければならない場合など、社内規定に沿って対応を行います。
稟議書での追加の書き方の例文・文例02
なぜ稟議書の追加を行わなければならないのか、その理由をまずは記載するやり方です。その理由如何により、稟議書そのものをやり直さなければならない場合があり得ます。このため、まずは稟議書の修正が必要であることを上司に伝え、その上司の了解の元で出し直しまたは修正を行っていきます。場合によっては、最初からすべてをやり直すことにつながるものです。
稟議書での追加の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
稟議書の追加を行う理由を明記します。その理由如何によっては稟議書のやり直しを命じられる場合もありますので、事前に上司等の決裁者の了解を口頭等でも得てから行うべき事柄です。稟議書の修正という形で追加を行うのか、あるいは稟議書そのものをやり直すのかによって、話は変わってきます。いずれにしても上司に事前に了解を得てから行うべきこととなるのが一般的です。
稟議書での追加の書き方の例文・文例03
誤字脱字等の軽微な内容の場合についてです。このとき、それほど重要な稟議書でない場合には、赤線で二重線を引き、稟議書を作成した人の訂正印を押印して事足りる場合もあります。その一方で、訂正印では済まされないような修正の場合には、差し替え等を指示されることもあり、その内容によって上司等の対応は分かれますから、その指示に従って対応を行わなければいけません。
稟議書での追加の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
誤字脱字等の軽微な内容の場合については、重要な稟議書でないと判断される場合には、稟議書を作成したものの修正印で事足りる場合があります。この場合にあっては赤線で二重線を引き、そこに修正印を押印するのが一般的です。また、それでは事足りない場合には差し替えを行いますが、差し替えるものと差し替え後のものとを両方セットで上司に見てもらうこともあり得ることです。
稟議書での追加の書き方の例文・文例04
そもそも最初に回した稟議書が書類が足りていない場合についてです。この場合には、なぜ追加資料を付けるのかその理由も付け加えて書類を追加することが求められます。理由については別紙という形で一筆記載するやり方が一般的ですが、そのやり方ではなく差し替えを指示する上司もいたりするなど、対応は分かれますので、その指示に従って書類を作成しなければならないこととなってきます。
稟議書での追加の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
最初に稟議書を上司に回し始めたものが、書類が実際には足りていない場合です。このときには、なぜ追加資料を付けたりするのかその理由を明らかにしなければなりません。その理由を別紙という形で追加させる場合もあり、このときには差し替え文書も理由を記載した文書も、稟議書の一式という扱いになってきます。なお、この対応で処理ができる場合かどうかは、上司に指示を仰がなければいけません。
稟議書での追加の書き方の例文・文例05
最終決裁者まで稟議書が回り、その押印がなされてしまった場合です。この場合はすでに稟議書として完結をしていると考えるのが一般的ですので、改めて稟議書を作成し、その稟議書を持って最終的な決断行動決定を行ったとするのが通常です。この場合には、最初の稟議書の意味が薄れますので、なぜ最初の稟議書で駄目だったのかの理由を明記した手紙等を添えて、上司の決裁を受けるのが通例です。
稟議書での追加の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
すでに最終決裁者まで稟議書が回り、その決裁がなされてしまった場合についてです。このときには、最初の稟議書は完結していますから、差し替える行為は通常は厳禁です。したがって、改めて稟議書を作成し、前回の決裁が降りた稟議書を付けて、どの箇所が修正されたものであるのかをはっきりさせます。その上で、最初の稟議書で間違えた箇所などの説明文を手紙等にして、付け足して関係者に再度見てもらうこととなります。
稟議書での追加の書き方で使った言葉の意味・使い方
そもそも稟議書とは、企業等において上司の了解を文書で得るための証拠書類です。すなわち、組織として行動する上で口約束ではなく証拠として後日まで残すために、この書類は作成されます。書式等は一般的にはすでに過去同じように作成されたものがあれば、それを参考にしながら作成を行えば済みます。もし全くない場合には、一から作成をしなければいけません。
稟議書での追加の書き方の注意点
稟議書を上司に回す理由等を最初に持ってくるなど一定のルールの下で行われます。その組織ごとで作成のルールは決められており、そのルールに従って稟議書の追加を行わなければいけません。差し替えとなる箇所を示したりあるいは最初からやり直しにするなど様々ですが、追加する場合にはなぜ追加するのか、その理由を一筆したためるのが通例となっています。
稟議書での追加の書き方のポイント・まとめ
稟議書の追加の場合には、追加する理由を明示しなければなりません。また、言葉などもですます調であったりあるいはである調など、その組織ごとのルールに従って作成を行います。稟議書は後日の鼓動などの根拠となる重要な文書で、またその行動の証拠となるものですから、企業内で文書作成の根拠が作成されているのが常です。そのルールに従って作成を行わなければならないものとなっています。
-

-
駐車場契約書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...
駐車場契約書の書き方についての雛形や書式は、ある程度決定しております。そして、実際の例文についても、インターネットで駐車...
-

-
アクションプランの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと...
アクションプランの書き方については、書式などは特に存在はしておりませんが、雛形や例文などについては、様々な言葉を使用して...
-

-
自治会での要望書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと...
自分の住んでいる地域に自治会が存在すれば、地域で何か要望があったときは自治会での要望書が必要です。自治会に要望を出すとき...
-

-
ゴルフノートの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...
ゴルフを本気で上達したいと思う場合、ゴルフノートを作ることがお勧めです。ノートには自分がプレーしたコースのことや成績のこ...
-

-
物を返す時のお礼文の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味など...
物を返す時のお礼文の書き方と用途ですが、まず、書き方は、相手によります。相手がとても親しい人の場合は簡単な言葉の手紙でい...
-

-
マインドマップの書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...
マインドマップとは、その人の心に見えてきた様々な気持ちや現象、物などを一度おもいっきり紙の上に書いて、自分がこれからどう...
-

-
博士学位論文の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...
大学院における研究にめどがつき、規定数の学術論文への掲載が進展し始めた頃から学位論文の準備をはじめます。十分に担当者と協...
-

-
ペット葬儀の香典袋の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味など...
ペットを飼っていない人またはペットを飼ったことのない人は、自分のかわいがっていたペットが死んでしまったときの悲しみがいか...
-

-
失礼なメール謝罪の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと...
学生時代ならまだしも、社会人になってから相手に失礼なメールを送ってしまい、不快な思いをさせたり、そのことが原因でトラブル...
-

-
お中元のお礼状の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...
お中元の送り状の雛形では、最初に暑中お見舞い申し上げます、で書き始める書式が一般的です。用途としては、いただいたお中元に...
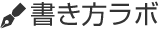





稟議書とは、一般企業等での部下から上司への伺いのことを一般的に指していうものです。民間企業ではなく役所等の場合は、起案書あるいは起案とも言い換えたりします。この文書を持って、必要な上司への説明及び了解を…